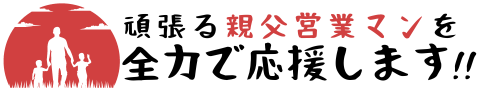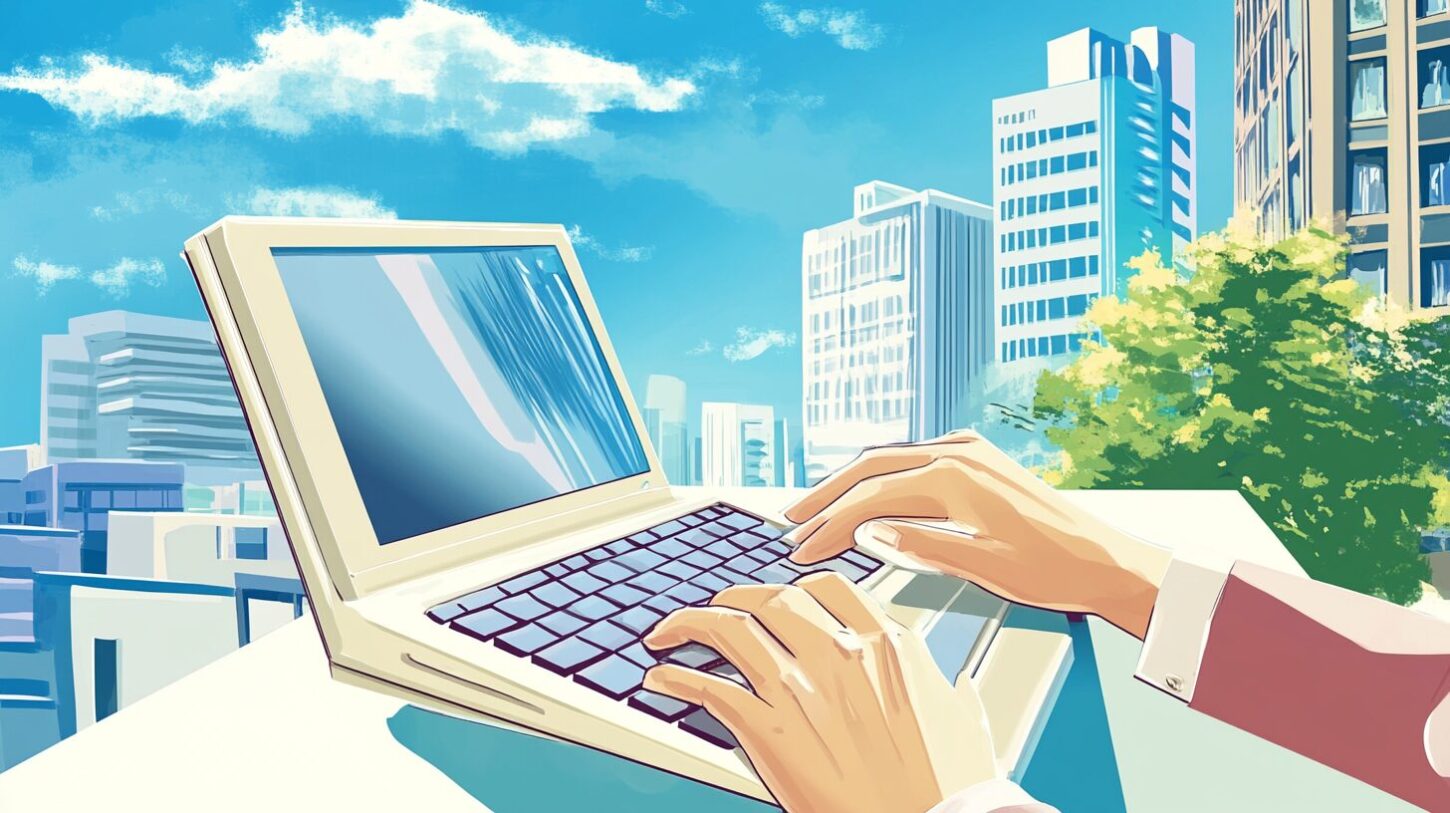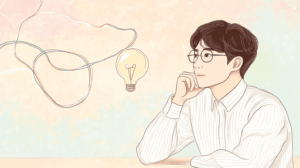「営業って、人間関係がすべてでしょ?信頼を築いて、あとはゴリ押し!」
……そんな時代も、たしかにありました。
でも、今はどうでしょう?
商品を紹介する前に、顧客がネットで調べ尽くしている。
提案書より先に、Googleのレビューがジャッジしてくる。
「気合と根性」で突っ込んだところで、「で、根拠は?」と一言で返される――
そう、営業も“数字で語る時代”に入ったのです。
とはいえ、営業現場のすべてが数字で割り切れるわけではありません。人間は感情で動きますし、関係性がモノを言う場面も当然あります。でも、感情と信頼を“裏打ち”するのが、データなんです。
たとえば――
「前回の施策で売上が12%アップしました」と言えるか。
「この商品、過去3カ月で●●業界では反応が良かったです」と見せられるか。
「御社の過去の購買傾向から、次の一手はこれです」と提示できるか。
この“数字の裏づけ”があるかどうかで、「説得力」も「信頼」も段違いになる。
そこで、登場するのがエクセルです。
「え、エクセル?ただの表計算ソフトでしょ」
……なんてもったいない!
エクセルは、ただの数字を「意味ある提案」に変える、営業マンの“思考ツール”なんです。
あなたは、アンドリュー・カーネギーをご存知でしょうか?
19世紀のアメリカで、鉄鋼王として成功を収めた実業家です。
貧しい移民からスタートし、莫大な富を築いた彼の強みは、徹底した効率化と数値分析力。
生産コスト、労働分配率、輸送経路、原材料価格…。彼はありとあらゆる数字を管理し、感情ではなく「数字の判断」で勝ち続けたんですね。
彼が今の時代にいたら、きっとこう言うでしょう。
「売上が欲しいなら、エクセルを開け」と。
本記事では、そんなカーネギーのビジネス術と、現代の営業実務におけるエクセル活用法を組み合わせながら、
「数字で語れる営業マン」になるためのヒントをお届けします。
人の心を動かす営業マンは、「共感力」も「数字力」も、どちらも持っています。
データで語り、共感で動かす。
そんな“これからの営業”のあり方に、少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこの先を読んでみてください。
“勘と経験”を超える営業力とは
「この案件、なんとなくイケそうな気がするんだよね」
営業の現場で、こんなセリフを聞いたことはありませんか?
あるいは、自分でも口にしたことがあるかもしれません。
もちろん、長年の現場経験からくる“勘”は、決して軽視できないものです。
むしろ、経験に裏打ちされた直感は、ときにデータをも凌駕する判断材料になり得ます。
でも――その「勘」、本当に当たっていますか?
そして、その「当たった理由」、ちゃんと説明できますか?
勘は大事、でも再現性がない
営業という仕事は、相手が“人間”である以上、常に不確実性を孕んでいます。
だからこそ、「感覚」や「空気を読む力」が重要なのも事実。
でも、それだけに頼っていると――成果に再現性が生まれません。
・あのときは売れたけど、今回は売れなかった
・あの人には響いたけど、別の人には刺さらなかった
この“ムラ”を放置したままだと、どれだけ優秀な営業マンでも、いつか限界が来ます。
だからこそ必要なのが、「勘と経験」にデータの裏づけを持たせる力。
つまり、感覚とロジックのハイブリッド営業なんです。
カーネギーは「数字で人を動かした」
ここで登場するのが、アンドリュー・カーネギー。
彼が鉄鋼業で成功を収めたのは、他社より「安くて良い鋼をつくれたから」ですが、その背景には、“徹底した数値管理”がありました。
カーネギーは工場の稼働率や人件費、輸送コストなどの数字を細かく追い、感覚ではなく、数字で「どこに改善余地があるか」を常に見抜いていました。
つまり――
「経験+数字」の視点が、事業を大きく動かしたわけです。
この考え方は営業にもそのまま応用できます。
データで「勝ちパターン」を見つける
たとえばあなたが、営業チームのリーダーだったとしましょう。
5人の営業マンのうち、Aさんは成績が良く、Bさんはイマイチ。
でも、なぜ差が出ているのかがわからない…。
そんなとき、エクセルで活動量・商談数・受注率を並べてみるんです。
・Aさんはアプローチ数が少ないけど、打率が高い
・Bさんは件数は多いけど、クロージングまでいっていない
このように、「何が違うのか?」が数字で見えてくる。
そして、その“勝ちパターン”をチーム全体に展開することで、再現性のある営業スキルが育つのです。
エクセルは、“再現性”を作るための道具
エクセルの強みは、ただの集計ではありません。
- 行動と成果の関係を見える化し
- どの施策が効果的かを比べられ
- 次に何をすればいいかが、数字でわかる
つまり、営業の「なんとなく」を、「なるほど」に変える道具なんです。
感覚は大事。でも、それを支えるのが、数字のロジック。
「たしかに、あのときも○○が効いてた」
「データを見たら、やっぱりこのタイミングでの接触がベストだった」
こんなふうに、感覚と数字が“合流”する瞬間が増えるほど、あなたの営業は磨かれていきます。
勘と経験を、“科学”で支える
「オレは数字が苦手でさ……」
そう思う人こそ、エクセルを味方にすべきです。
なぜなら、エクセルは「頭の中の曖昧さを、整理してくれるツール」だから。
カーネギーがそうだったように――
“鋭い感覚”と“冷静な数字”が合わさったとき、営業力は次のステージに進みます。
さあ、次章ではそのカーネギーが、どのようにビジネスを築いていったのか。
歴史に学ぶ「データで勝つ戦略」をひも解いていきましょう。
アンドリュー・カーネギーの“数字思考”に学ぶ
アンドリュー・カーネギー――
19世紀のアメリカを代表する実業家にして、鉄鋼王。貧しい移民少年からスタートし、のちに世界有数の富を築いた彼のビジネス手法は、実は「数字で動く営業マン」にとっても、学ぶべきヒントに満ちています。
感覚ではなく、“確率”で動く男
カーネギーのすごさは、ビジネスの意思決定において「感覚」や「空気」を頼らなかったこと。
彼は、どんなに小さな判断でも必ず数字で“筋のよさ”を測ってから動いたのです。
・どの炉で鋼を作れば、もっとも歩留まりがいいか?
・どの労働者のチームが、生産性が高いのか?
・どのルートを使えば、原材料のコストが抑えられるのか?
その1つ1つを、徹底的に記録し、比較し、改善した。
言い換えれば、カーネギーの強みは――
「自分の感情を排除して、“数字がYESと言っている方”に賭ける勇気」だったのです。
「数字を集めて、意味を見つける」力
カーネギーの時代、当然エクセルなどは存在しません。
彼のデータ管理は、帳簿とノートと人力。
でも彼は、そこから「意味あるパターン」を見つけ出す力に長けていました。
・どの顧客が定期的に大口発注をくれるか
・納期にうるさい顧客と、納期より価格重視の顧客の傾向
・季節ごとの需要のズレ
こういった“数値に潜む傾向”を、感覚ではなく記録と観察によって導き出していた。
いわば、手書きのピボットテーブルのようなものです。
データは「選ぶ力」をくれる
ここで、あなたの営業に置き換えてみましょう。
たとえば――
・月に20件の商談をこなしているけど、成約率は20%
・提案Aの成約率は15%、提案Bは35%
・訪問回数が2回を超えた顧客は、80%以上が受注につながっている
こういう数字をしっかり把握していれば、「今月どこに注力すべきか」は自然に決まります。
逆に、数字がなければ、「なんとなく」で時間を浪費することになる。
カーネギーは、数字に従って“選ぶ力”を磨いたからこそ、少ない労力で最大の成果を出せる構造を作り上げたのです。
カーネギーにエクセルがあったら?
もし彼が現代に生きていて、エクセルを手にしていたら――
きっと、マクロや関数を駆使して、コストの最小化と売上の最大化を瞬時に見抜いていたでしょう。
彼のスタイルは、こう言い換えられます。
感情ではなく、数値で意思決定する。直感ではなく、パターンで判断する
これはまさに、エクセルが得意とする領域ですよね。
カーネギー式営業術=“数字を読む力”+“人を動かす力”
カーネギーがすごかったのは、「数字」だけではありません。
彼は、人の心の動きを深く理解していた“共感の人”でもありました。
・労働者の待遇改善に取り組んだり
・競合他社の社員に感謝の手紙を送ったり
つまり、彼の営業スタイルは――
「数字で戦略を練り、共感で人を動かす」
という理性と感情の両輪型だったのですね。
“現代の営業マン”が学ぶべきカーネギーの視点
営業とは、「人を動かす仕事」です。
そのためには、“数字で納得”させ、“感情で後押し”する必要があります。
カーネギーの時代は手計算。
でも今の僕たちには、エクセルという最強のツールがあります。
・数字の根拠をサッと出す
・説得力ある資料を5分で仕上げる
・提案の精度を裏づける“データの盾”を持つ
これができれば、「売れる営業」は技術で再現できるんです。
次章では、現代の営業マンが“勘”を超えるために、どうやって エクセルを活用し、データに基づく意思決定を行うのか。その進化と実践を詳しく見ていきましょう。
データに基づく意思決定の進化
「経験がすべて」「勘がモノを言う」――
かつての営業現場では、そんなセリフが飛び交っていました。
たしかに、経験は貴重です。
でも、“経験だけ”で乗り切る時代は、もう終わりを迎えつつあります。
いま求められているのは――「経験×データ」で意思決定する力。
勘は“当たることもある”、データは“再現できる”
ベテラン営業マンの「感覚」には、確かに価値があります。
「なんか、この人は買いそうだな」
「この案件は、稟議通るまでに時間かかりそう」
こうした直感は、長年の積み重ねでしか得られないものです。
でも――
勘は他人に教えられないし、再現性がない。
部下に伝えるにも、根拠を示すにも、「なんか…」では済まないんですよね。
その点、データは違います。
・提案Aの成約率:42%
・提案Bの成約率:17%
・初回面談からクロージングまでの平均日数:18日
こうした数値があるだけで、意思決定の精度と説得力が、格段に上がる。
数字は「自分の営業を可視化する鏡」
営業の世界には、曖昧な部分が多く存在します。
でも、それを放置していると、改善も育成もできない。
エクセルで数字を追えば、自分の営業が「どこでつまずいているか」が見えるようになります。
・面談数は多いのに、成約率が低い?
→ヒアリングが甘いのか、提案内容がズレてるのか
・成約率は高いけど、商談数が少ない?
→見込み顧客の発掘が足りてないのか
このように、数字は自分の営業スキルを“言語化・数値化”する手段なのです。
データドリブン営業=“打率”で動く営業マン
野球に例えるなら――
これまでは「気合いで振るホームラン狙いのバッター」だった営業が、これからは「ヒットゾーンを狙って打率を上げていく選手」に変わるべきです。
つまり、営業活動を“打率”で捉え、
・どのタイミングで声をかければ成約率が高いのか?
・どんな資料のときに、稟議がスムーズに通るのか?
・どのルートでアプローチすれば、レスポンスが早いのか?
こうした“パターン”を、数字から読み取っていく。
これが現代の“データに基づく営業”のスタンダードです。
エクセルは、「感覚」に“根拠”を持たせるツール
ここで重要なのは、「感覚」と「データ」、どちらかに寄るのではなく、両方を掛け算する姿勢です。
「たぶん、この顧客にはこの提案が響きそうだ」という仮説があったら、「過去に同じ業界・同じ役職の顧客で、似たパターンがどれだけあったか?」を、エクセルで検証してみる。
すると、感覚に「再現性」が生まれます。
つまり、カンを“読み”に変えることができるのです。
データに基づく営業は、“人の信頼”も獲得する
実は、数字で語る営業の最大のメリットはここです。
上司に報告するとき。
部下に教育するとき。
そして何より、顧客に提案するとき――
「これまでの傾向では、〇〇のケースで反応が良く、御社の条件にも合致しています」と数字を添えられるだけで、説得ではなく納得が生まれる。
カーネギーが信じていた“数値の裏づけ”とは、まさにこの力だったのでしょう。
次に必要なのは、「数字を活かすための設計力」
ここまで読んで、
「なるほど、数字が大事なのはわかった。でも、実際どう使えばいいの?」
と思ったかもしれません。
次章ではいよいよ、営業戦略をどうエクセルで“設計”し、意思決定につなげていくかを解説します。
目の前の数字を、「判断力」に変える力――それが、売れる営業マンの“次の武器”になります。
エクセルを活用した営業戦略の立案
営業って、結局は「戦略×行動」のかけ算です。
でも、多くの営業現場ではこの「戦略」が、経験と勘に頼りきりだったりします。
「とりあえず今月は、アポをたくさん取ろう!」
「なんとなく反応よさそうな業界から当たってみよう!」
……これでは、“行き当たりばったり営業”になってしまう。
だからこそ、いま必要なのは――エクセルを使った「戦略の見える化」です。
戦略なき営業は、ゴールのないマラソン
まず前提として、「戦略」とは“仮説”です。
「こうすれば、売れる確率が高くなるはずだ」という思考の設計図。
これを持たずに営業すると、どこに向かっているかも分からず、走り続ける羽目になります。
たとえば、
- 顧客A:今月すでに3回訪問している
- 顧客B:前回のアプローチから3か月放置中
- 顧客C:高額案件の見込みがあるのに、訪問はゼロ
……こうした“機会ロス”や“偏り”は、日々の忙しさの中では気づきにくい。
でも、エクセルに落とし込めば、一目瞭然なんです。
エクセルで「営業マップ」をつくろう
営業戦略を立てる上でおすすめなのが、営業マップの作成です。
営業マップとは、エクセルで以下のような情報を一覧化したシートのこと。
| 顧客名 | 予算規模 | 業界 | 最終接触日 | 温度感 | 次回アクション | 担当者コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 500万 | 製造 | 5/1 | 高 | 5/10訪問 | 競合も動いてる |
| B社 | 300万 | IT | 2/25 | 低 | 5/15メール | 一度断られたが興味あり |
こうした情報を一覧にするだけで、
- どの顧客に注力すべきか?
- 優先順位はどうか?
- 案件の「死にかけ」サインは出ていないか?
が視覚化され、戦略的なアプローチが可能になります。
ピボットテーブルで「戦略の俯瞰」もできる
さらに、ピボットテーブルを使えば、
- 業界別の進捗
- 地域別の商談数
- 月別の成約率
など、複数の軸で営業活動を俯瞰できます。
これにより、「今月、どの業界が反応いいのか?」「地域別に成果が偏ってないか?」など、“営業戦略の舵取り”がしやすくなる。
戦術(訪問、架電)は現場が回すもの。
戦略(どこを攻めるか)は、数字を見て判断するもの。
エクセルが、この「戦略の司令塔」になってくれるのです。
カーネギーもやっていた、リソースの最適配分
アンドリュー・カーネギーは、鉄鋼王としてのキャリアの中で、「どこに資源(ヒト・カネ・モノ)を投下すべきか」を常に考えていました。
彼が成功できたのは、すべての判断に“数字”を持ち込んだから。
- 利益率の低い工程は切り捨て
- 回転率の高い販路に人員を集中
- 時間がかかる案件には、見切りをつける
営業でもまったく同じです。
自分の時間という“資源”を、数字で管理し、優先順位をつける。
エクセルを使えば、営業活動も“投資判断”のように管理できるんですね。
数字を使えば、“戦略的な営業会議”ができる
「今月は、頑張ります!」
「とにかく件数を増やします!」
そんな根性論ではなく、
- 「今月は、B業界での成約率が高いので、そこに注力します」
- 「XX社は先月からの接触が続いており、ここで一押し必要です」
と、数字と根拠に基づいた報告・提案ができる営業チームは、強いです。
エクセルで日々の行動を可視化し、分析し、戦略に落とし込む。
それだけで、営業の「再現性」と「説得力」は爆上がりします。
エクセルによるデータ分析の実践
戦略が立ったら、次にやるべきは「振り返り」と「改善」です。
ただし、ここでありがちなのが――
「感覚的な振り返り」に終始してしまうこと。
「今月は手応えあった」
「たぶん、あの提案がよかった」
「なんとなく、あの業界は反応悪い」
……全部、“気のせい”かもしれませんよね。
だからこそ、営業において最も信頼できる相棒が、やっぱりエクセルなんです。
STEP1:売上データを分解して「どこで成果が出たか」を明らかにする
たとえば月次の売上を振り返るとき。
ただ「今月は売上500万円」と眺めても、改善にはつながりません。
重要なのは、「なぜその結果になったのか?」を読み解くこと。
エクセルで以下のように“要素分解”してみましょう。
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| アプローチ件数 | 100件 |
| 商談化率 | 20% |
| 成約率 | 30% |
| 平均単価 | 83,333円 |
| 成約件数 | 6件 |
| 総売上 | 500万円 |
ここで見えてくるのは、
- アプローチ数は十分でも、商談化が低い?
- それとも成約率が課題?
- もしかすると、単価アップの余地があるかも?
エクセルは、ただの結果を「打ち手に変える」ツールでもあります。
STEP2:ピボットテーブルで“営業のクセ”を炙り出す
「特定の業界だけ、なぜか受注率が低い」
「地域によって反応がバラバラ」
「ある営業担当者だけ、数字が伸びない」
――こんな“クセ”を見つけるのに便利なのが、ピボットテーブルです。
使い方は簡単。
- データ一覧(商談データ、顧客属性、結果など)を準備
- 「行」=業界や地域、「列」=月別、「値」=売上や成約数で集計
- 気になるところにフィルターや並び替えをかけて、傾向を見る
エクセルが、「なんとなく」の違和感を数字で証明してくれます。
STEP3:「見える化」すれば、チームの改善が始まる
グラフ化も強力です。とくに、
- 成果の推移を折れ線グラフで
- 業界別売上を棒グラフで
- 営業担当者別の成績をレーダーチャートで
……など、見える化するだけで、気づきが生まれる。
数字が目に見える形になると、
- 「ここは改善が必要だな」
- 「この人のやり方、真似しよう」
- 「今月はどこを攻めようか」
と、チーム全体が前向きな議論をしやすくなります。
営業は個人プレーのようで、実はチーム戦。
エクセルは“共通言語”として、戦術共有の土台になるんです。
カーネギーも「分析の鬼」だった
鉄鋼王カーネギーは、売上よりもまず「コスト構造」に注目していました。
- どこでロスが出ているのか
- どの工程が利益を圧迫しているのか
- 輸送費や人件費を最適化できないか
彼は、「儲かっているか」より「効率的かどうか」に目を向けていたんです。
これ、営業でもまったく同じです。
- 売れてるように見えるが、実はムダが多い案件
- 成約したけど、利益率が極端に低い業種
- たくさんアポは取ってるけど、時間単価が異常に悪い営業活動
……こうした“非効率”は、数字を分解しなければ見えてこない。
カーネギーは手書きの帳簿でやっていたことを、私たちはエクセルで、もっと速く・もっと深くできるんです。
未来の営業スキルとエクセルの役割
「AIに仕事を奪われる時代」――そんな言葉をよく耳にするようになりました。
でも私は思うんです。
奪われるのは、“考えずにやっている仕事”だけだと。
逆に言えば、「人間だからこそできる営業」って、これからもっと価値が上がる。
そして、その価値を高めるベースにあるのが、やっぱりエクセルなんですよね。
“作業”はAIに、“思考”は人間に
たとえば、
- 顧客情報を自動で入力する
- メール送信を自動化する
- 見積書を自動生成する
――これらは、すでにAIやRPAが得意とする領域になっています。
じゃあ営業マンは、何をするのか?
それは、「なぜこの提案が必要か」を考え、言葉にして伝えること。
つまり、“数字を読んで、意味づけする”仕事です。
そしてその“読み解き”の起点になるのが、エクセル。
エクセルは「考える営業」の筋トレツール
営業職に必要なスキルは、どんどん複雑化しています。
- 論理的思考力(なぜこの施策が効果的なのか)
- 顧客理解力(この人は何に困っているのか)
- 情報編集力(どう伝えれば響くのか)
これらを鍛えるには、ただ営業に出るだけじゃダメなんです。
エクセルで数字を追い、仮説を立て、検証していく。
この地道なプロセスこそが、「営業頭脳」を育ててくれます。
たとえるなら、エクセルは“営業のジム”。
データの海で泳げる営業マンは、どんな環境でも成果を出せるようになります。
“共感”と“数字”を両輪で持つ営業が最強
ここまで読んでくださったあなたは、きっともうお気づきでしょう。
営業という仕事は、ロジックだけでもダメ。感情だけでもダメ。
必要なのは、「共感」と「数字」の両輪です。
- 相手の悩みに寄り添い、
- 数字で未来を見せてあげる。
これが、人を動かす営業の本質です。
アンドリュー・カーネギーがそうだったように、“信頼”を数字で裏打ちできる人が、これからの時代をリードしていくんです。
エクセルの先にある未来へ
もちろん、エクセルも万能ではありません。
より大規模なデータ管理には、CRMやBIツールが必要になるでしょう。
より複雑な分析には、PythonやTableauのスキルが必要になるかもしれません。
でも――すべての出発点に、エクセルがある。
- まずは小さな表から始める。
- 自分の数字を、自分で集計する。
- そこに意味を見出す。
こうした「データと向き合う姿勢」こそが、営業職としての基礎体力になります。
営業の未来は、「人間力 × データ力」
最後に、こんな問いを投げかけて終わりにしましょう。
あなたは、数字を“見る”営業マンですか?
それとも、数字を“語れる”営業マンですか?
未来の営業は、カーネギーのような鋭い洞察と、現代的なツールを組み合わせてこそ、真価を発揮します。
あなたも、エクセルを味方につけてください。
“人を動かす営業”への扉は、そこから始まっています。